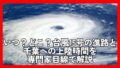「ジョッキーになりたいのに、なぜ“人がいない”と言われるのか」。
実は「騎手不足」といっても、中央競馬(JRA)と地方競馬(NAR)で状況や要因は異なり、育成や採用の入口となる“競馬学校”の入学難度の高さ、在学中の体重管理の厳格さ、地域ごとの人員偏在、さらに地方現場では厩務員との兼務が一般的なことなどが絡み合っています。
本記事では、JRA競馬学校の最新の受験実態(倍率・合格者数・選考内容・体格基準)を公式情報で丹念に紐解きつつ、「偏差値」という言葉の誤解を整理し、地方で起きている人手不足の構造と制度面の手当(期間限定騎乗、女性騎手の減量制度など)まで、どなたでも分かる言葉で立体的に解説します。
「ジョッキーがいない」と言われる本当の理由
ジョッキーが足りない、という言説は主に地方競馬で顕著です。
地方では複数主催者が分散開催する一方、各場の所属騎手数が十分でないケースがあり、他地区からの「期間限定騎乗」で穴を埋める運用が常態化しました。
若手が騎乗機会を求めて一時移籍する動きは本人の成長にも資する半面、受け入れ側にとっては慢性的な人員不足の緩和策でもあり、裏返せば厩舎現場の人手不足(騎手の厩務員兼務が多い)が背景にあります。
この「期間限定騎乗の活発化」と「騎手不足」は表裏一体だ、と専門コラムは指摘します。
また、例えば笠松競馬は不祥事の後遺症も影響して専属騎手が9人まで減り、他場と比べても極端に少ない状況で、期間限定騎乗者の帰郷などで一時的に更に薄くなる局面も生じています。
1999年に36人いた時代から4分の1まで縮小したという現場の肌感は、再生に向けた人材確保の難しさを物語ります。
JRA競馬学校「騎手課程」の実像(受験資格・体格基準・試験内容)
JRA競馬学校の騎手課程は、年齢・学歴・体格・視力などの基準を満たした志願者を対象に、一次・二次の厳格な選抜を行います。
年齢は入学年度の4月1日時点で15歳以上20歳未満、学歴は中学校卒業以上または同等の学力が必要です。
視力は両眼で0.8以上かつ左右0.5以上で、矯正は可能ですが、使えるのはソフトコンタクトレンズのみという詳細規定が明示されています。
体重は応募時点で年齢区分ごとに上限が定められ、在学中も上限超過は「いかなる理由でも不可」、卒業時の上限体重(指定体重)は全員一律49.0kgと、体重管理の厳格さが制度に組み込まれています。
選考は一次(身体検査=体重・身長、運動機能検査、国語・社会の学科、本人人面接)と二次(身体検査、一次と異なる運動機能検査、騎乗適性検査・厩舎作業審査、本人人面接・保護者面接)で構成され、健康診断書の提出も条件化されています。
応募段階で基準に満たない場合は受験不可とされる点も、入口の狭さを際立たせます。JRA(募集要項PDF)
倍率の実態を数字で読む(42期〜44期)
最新期の動向を見ると、2025年度の第44期は応募198名→一次合格29名→最終合格9名で、入学者9人という結果でした。
報道は「応募者総数198人から9人が入学=倍率22倍」と説明しており、定員の公表がない中でも実効的な狭き門ぶりが見て取れます。
その前年(第43期)は、発表時点で「合格者10人」とされましたが、入学式の報道では9名の名前が紹介されています。
発表から入学までの間に進路変更や辞退等が生じることは稀ではなく、数字の読み解きには「合格者」と「実際の入学者」を区別する視点が欠かせません。
さらに遡って第42期(2023年度)は応募192人、一次受験174人、二次受験29人、最終合格7人という公式発表が報じられました。
3期分を通覧すると、応募は約200人規模、入学は一桁後半〜10人程度に留まる年が多いことが分かります。これが結果として、世間で「倍率が高い」「狭き門」と語られる根拠です。
簡易サマリー(42〜44期の公表値)
- 第42期(2023年度入学)…応募192→最終合格7
- 第43期(2024年度入学)…合格発表10→入学式9
- 第44期(2025年度入学)…応募198→合格9(=22倍)
「偏差値」は公表されていない——言葉の誤解を解く
受験難度を「偏差値」で語る民間サイトはありますが、JRAは入試の学力偏差値を公表していません。
そもそも選抜は学科だけでなく体格・視力・運動機能・騎乗適性・厩舎実務適性・面接の総合評価であり、一般的な受験偏差値の物差しを当てはめるのは正確ではありません。
ネット上の「資格難易度偏差値」などは独自指標で公式なものではない点に留意が必要です。
受験に関して信頼すべき一次情報は、JRAの募集要項・試験実施要領・合格者発表等の公的資料です。
地方競馬の「騎手不足」はなぜ起きるのか(構造と地域偏在)
地方では、売上の回復と開催の活発化に対して、騎手・厩舎の人員が十分に追いつかない局面が出ています。
若手が騎乗機会を求めて他地区に一時移籍する「期間限定騎乗」は、本人の経験形成と受け入れ側の人員不足対策を兼ねる実務的な仕組みで、2006年にNARの取りまとめで平地全場で制度化された経緯が整理されています。
制度が常態化するほど、受け入れ側の“慢性的人員不足”の裏返しでもあることが分かります。
笠松競馬の事例は象徴的で、専属騎手の数が長期的に減少、他地区の期間限定騎手が支える構図が続くなか、短期免許者の帰郷や不測の離脱で一時的に体制が薄くなる脆弱性も露呈しました。
かつての「地方競馬の聖地」からの再生には、騎手だけでなく厩舎人員全体を巡る信頼と人材の循環を回復させることが不可欠、という現場の声が伝わります。
ルールと制度のアップデート(見習減量・女性騎手減量・交流)
騎手の「減量制度」は、経験の少ない見習騎手や女性騎手、障害競走の新規騎乗者などに、所定の要件に応じて負担重量を軽くする仕組みです。
JRAの用語解説では、(特別戦・ハンデ戦を除く)一般競走で女性騎手・見習騎手等に減量が適用されること、勝利度数に応じた段階的な記号・減量幅が整理されています。
この制度は若手や多様な人材の騎乗機会を広げる狙いで重要な位置づけです。
特に女性騎手については、2019年3月1日から「50勝以下は4kg、51〜100勝は3kg、免許5年以上または101勝以上でも2kg」という永続的な減量対象とする新制度が導入され、実績ある女性騎手の騎乗機会拡大に寄与しました。
制度変更の具体的な開始時期と数値が公式発表として報じられています。
受験を目指す人が知っておくべき「合格の現実」
現実的な第一関門は、応募段階での体格・視力基準をクリアすることです。
JRAは視力基準を明記し、矯正はソフトコンタクトレンズのみ可としています。
体重は年齢区分に応じた上限が定められ、在学中の上限超過は「いかなる理由でも不可」、卒業時の指定体重は一律49.0kgという厳格な運用です。
日常的な体重管理・運動機能・適性の積み上げが合格の前提であり、一次・二次では学科(国語・社会)に加えて、運動機能・騎乗適性・厩舎作業適性・面接まで評価されます。
準備は学力対策だけでなく、身体作り・視力管理(必要なら早めの矯正相談)・厩舎作業の理解まで一体で進めることが肝要です。
地方競馬の育成機関と「もう一つの入口」
地方競馬で騎手を目指す場合の入口は「地方競馬教養センター」です。
ここで所定の育成課程(2年)を修了し、地方の騎手免許試験に臨む流れが基本です。
NARの公式サイトには騎手候補生募集の案内や要項が公開されており、入所後は実践的な騎乗技術と厩舎実務を徹底的に学びます。
地域の騎手偏在や人員不足の是正には、こうした育成ラインの十分な機能発揮と、受け入れ先主催者の魅力・環境整備が不可欠です。
まとめ:入口は狭い、だからこそ「準備」と「構造理解」を
- JRA競馬学校は応募約200人規模に対し入学一桁後半〜10人程度の年度が多く、44期は応募198→入学9で概算22倍。公表されるのは「偏差値」ではなく、厳密な体格・視力・適性基準と多面的選抜です。
- 地方の「騎手不足」は、厩舎現場の人手不足や地域偏在、期間限定騎乗の常態化と密接。制度(2006年の制度化)と現場運用を理解しつつ、育成ラインの強化と受け入れ環境の魅力づくりがカギです。
- ルール面では見習・女性騎手の減量制度が騎乗機会を下支え。2019年から女性の永続的減量(4kg/3kg/2kg)が導入され、多様な進路に光が射しています。